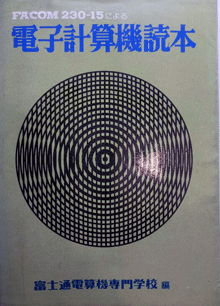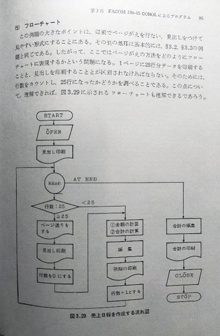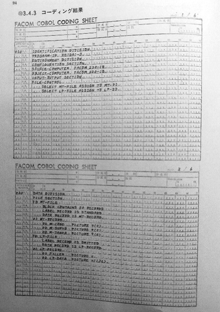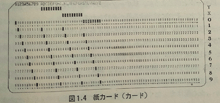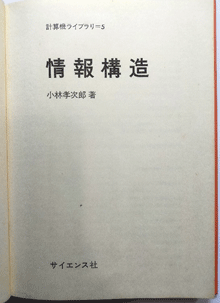| |
||||||||||||||||||||
| リレー随筆 「鮭っ子物語」 No.263 |
令和7年9月発行 | |||||||||||||||||||
| コンピュータとの出会い (その2) ~そして専門学校へ入学~ |
||||||||||||||||||||
| *本稿はリレー随筆#259(2025年5月1日号) 掲載のエッセイのつづきである。 |
|
|||||||||||||||||||
| 1977年、秋も深まった頃、夕ご飯の後、家にトヨタのセールスマンが訪ねてきた。父が呼んだらしかった。私は勤務先である関川村辰田新にある横山商店のガソリンスタンドまで自転車で通っていたのだが、自動車を買ってやるから東京に行くのを止めて、関川村にいろというのが父親の考えだった。 しかし、私の決意は揺らぐことなく12月末でガソリンスタンドを辞めた。 富士通電算機専門学院には2月に願書を提出して、3月11日・12日に大田区蒲田で入学試験を受けた。 次の週に届いたシステムズエンジニア課程の合格通知を見て、思わず小躍りしてしまった。 4月から専門学校のシステムズエンジニア課程での授業が始まった。富士通電算機専門学院は大田区蒲田の富士通システム ラボラトリのA棟の4階にあった。教室がシステムエンジニア課程、プログラマー課程の2部屋、図書室が一部屋、あと休憩室があった。 座学の授業は教室で行われた。コンピュータを使う実習はB棟のコンピュータの置いてある部屋で行われた。B棟にはカフェテリア食堂(朝・昼・夕食)があり、カレー、ラーメンのコーナー、定食のコーナーが選べた。眺めがよく羽田の海の方まで見渡せた。売店もあり、富士通羊羹が売っていた。 COBOL(コボルという事務処理向けのプログラミング言語)から勉強した。講師は師岡先生で学校まで箱スカ(当時一世を風靡したスカイラインの人気モデル)で通っていた。私にとってCOBOLは未知の世界だったが、師岡先生は初心者の私たちに丁寧に教えてくれた。 当時のコンピュータの実習はこんな感じだった。 実習問題を理解して、処理の手順をフローチャートに書く。フローチャートを見ながらプログラムをコーディング用紙に書いていく。出来上がったコーディング用紙をカードパンチ会社に出して、1行を1枚のカードにパンチしてもらう。仕上がったカードの束をカードリーダー装置にセットして、カードを読み込み、プログラムを実行して、結果がプリンタ装置に出力された。 師岡先生とは後日、私が45歳になった時、東京都労働経済局の先生の退職の会で偶然、お会いして挨拶をしたが師岡先生の反応は冷めたものだった。 私からすると25年ぶりに会った師岡先生は、COBOLを教えてくれた全能の神のような存在で、かなりテンションが上がっていた。 続いて、FORTRAN(フォートランという科学技術計算向けのプログラミング言語)を勉強した。私にはFORTRANの配列の考え方が理解できなかった。週末、隣の席の渡部くんに泊まりがけで教えに来てもらった。 渡部くんは配列をタンスの引き出しに例え、引き出しに服を入れるように値を入れ、引き出しに入った値を計算に使うことを教えてくれた。おかげで配列を理解でき、霧が晴れるようにFORTRANの世界が見えてきた。 渡部くんは鳥取県米子市の商業高校を卒業して、専門学校にやってきた。商業高校では実習でコンピュータを使う時間があり、コンピュータに対して、手慣れた感じがした。専門学校修了時に優秀賞をもらっていた。 彼はコンピュータの仕事に就いてからは新幹線ホームの掲示板の表示システムの仕事をやっていた。5年くらいして、仕事に行き詰まり、会社を辞めて、バイクで北海道ツーリングをしてから故郷の米子市に帰り、郵便局に定年まで勤めた。 私は渡部くんのお陰で専門学校を修了することができ、コンピュータの仕事に就けたと今でも感謝している。 3つ目はアセンブラ(低水準のプログラミング言語)はパナファコムU200ミニコンの詳しい構造とその命令体系、アセンブラ言語によるプログラミングを勉強した。 アセンブラ語のステートメントは個々の機械語命令の記号表示なので、コンピュータのハードウェアを直接制御するために使われる。 専門学校でお世話になった先生たちのことを紹介しよう。 富士通汎用機のAIM DB/DC(オンラインデータベースシステム管理)を教えたもらったのは米津先生。 演習ではAIM DDL(定義言語)でテーブル定義の作成や変更を行った。オンライン問合せプログラムの動作環境を定義して、問合せプログラムを実行した。データベースにセットしたデータがデイスプレイ装置に表示された時には思わず、「やったー!」と声を上げてしまった。 ハードウェアの授業を担当したのは山口先生で、山田博さん(当時、富士通の開発事業部長を務めていた)が著した『コンピューターアーキテクチャ』をテキストにして、コンピュータ発展の歴史、コンピューターアーキテクチャの基本、記憶の構造—仮想記憶方式—、高速計算機、アレイプロセッサ、RAS(信頼性、可用性、保全性)、ネットワークアーキテクチャを教えてもらった 基本算法の授業は高橋先生の担当で小林幸次郎著『情報構造』をテキストにして、情報の表現、線形リスト、手続きの回帰的呼び出しとスタック、木、多リンク構造とリスト、LISP(リスト処理用プログラム言語)、記憶領域の管理、表と探索について教えてもらった。 システムズエンジニア課程の担任の大野先生は、私たち、55名が専門学校に入った年に富士通の金融部門から蒲田の教育部の富士通電算機専門学院にやってきた。 私が24歳の時、偶然浜松町の立ち食いそば屋で会った、これから仕事先に行く、忙しい時間だった。大野先生は富士通の金融の営業をしていると話してくれた。 私は港区海岸にある富士通の代理店で出版社の経理システムの設計をしていると話した。大野先生は「身体に気を付けて、がんばれ」と言ってくれた。 富士通電算機専門学院を卒業したのは1978年3月であった。当初、上京することには反対であった父に卒業と就職について報告すると、父は寂しそうであったがにこりとほほ笑んでくれた。「ところで富士通は何を運ぶ会社なんだ」と聞かれた。 当時、日通が運送会社で有名だったので、父は富士通は運送会社だと思っていたらしい。 |
||||||||||||||||||||
| 東京村上市郷友会ホームページ リンク | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 表 紙 | WEB情報 | サイトマップ | バックナンバー | 検索・リンク 発行:デジタルショップ村上 新潟県村上市・岩船郡7市町村 月刊デジタル情報誌 2001年1月1日創刊 (c)2001~murakami21.jp All rights reserved Produce by Takao Yasuzawa |
||||||||||||||||||||