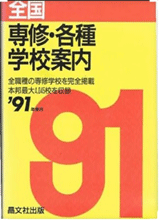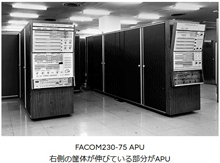1977年(昭和52年)3月に村上高校を卒業して、関川村辰田新にある横山商店のガソリンスタンドで働きはじめた。右も左も分からない私は3才年上の先輩に1から仕事を教えてもらっていた。仕事にも大分なれた午後、仙台方面から車が入って来た。お客様はカードで満タンと言ったので給油を始めた。
クレジットカードを先輩に見せると準備をしてくれた。お客様から預かったカードと初めて見る売上伝票用紙(注1)をインプリンタ装置(注2)の上に置き、インクローラーを押し付けながら左から右へ往復する。売上伝票をお客様のところに持って行き、名前を書いてもらった。そして、納品書をお客様に渡し、残りの伝票を事務のおばさんに渡した。初めて体験したクレジットカードのお客様の伝票処理だった。その後、店長にクレジットカードのお客様の伝票はどうなるのか、聞いてみた。店長によると、売上伝票は月末、まとめられて、東京にある共同石油の事務センターに送ると、コンピュータ処理され、翌月に会社の口座に給油料金が振り込まれるとのことだ。
なお、1960年代から1970年代にかけての日本におけるコンピュータを取り巻く状況については(注3)で簡単な流れを説明しているので参照されたい。
はじめて見たクレジットカード、コンピュータという言葉が頭に引っかかった。週末、坂町の川口書店(注4)に行って、コンピュータの専門学校が載っている、『全国・各種学校案内』(注5)という本を買い、その日からコンピュータ専門学校のところを読み始めた。計算機内部の事を教える、ソフトウェア科とハードウェア科、システム開発を教える、プログラミング課程とシステムズ・エンジニア課程、ソフトウェア全般を教える情報処理科などがあった。
専門学校は学校法人がやっている所がほとんどだったがメーカーが経営する専門学校(注6)に強く惹かれた。専門学校でコンピュータを勉強する事を考えると単調だったガソリンスタンドでの仕事が楽しくなった。
| 注と参考資料 |
| (注3)この頃の日本を取り巻くコンピュータの状況は以下の通りである。 |
1964(昭和39年)東京オリンピックで競技の計測と結果の印刷に使われた。
1970(昭和45年)大阪万博で日本IBMのパビリオンにおいて、コンピュータの操作体験の展示が行われた。
1971(昭和46年)世界初の新聞製作システム(日本経済新聞社・朝日新聞社)が導入された。
1972年(昭和47年)札幌オリンピックでは競技結果を計測して、結果を印字、複写増刷して配布した。
(以上、全て日本IBMのホームページから引用。『日本IBM 創立から80年の軌跡』
https://www.ibm.com/ibm/jp/ja/history.html)
(注4)(注4)坂町の川口書店
坂町の川口書店は、中学の頃から『ミュージックライフ』、『ライトミュージック』、高校になってからは村上龍の芥川賞受賞作『限りなく透明に近いブルー』が載っている月刊雑誌『文藝春秋』を買っていた関川村にあった本屋の10倍くらい広く感じていた書店だった。なお、高校時代、ジャスコの1階にあった書店は坂町の川口書店の支店である。
(注5)『全国・各種学校案内』(晶文社出版)
全国の専門各種学校を分野ごとに編集。学費・募集学科など各学校の入学情報掲載。諸官庁設置校の情報も併せて掲載されている。
(注6)専門学校
私が入学した富士通電算機専門学院は情報処理技術者の養成を目的として、昭和42年5月設立された学校で、コンピュータ・メーカー富士通(注7)が経営するわが国唯一の電子計算機専門学校である。メーカーの持つ豊富な技術・経験・設備により、常に先端的な教育活動を展開している。
(注7)コンピュータ・メーカー富士通
当時のコンピュータ・メーカーとしての富士通について
1974年、汎用機「FACOM Mシリーズ」(注8)を発表
1975年、アムダール社の超大形機「470V/6」(注9)をNASAに納入
1976年、大型コンピュータの製造の為、沼津工場を開設、IBM互換機(注10)「FACOM Mシリーズ」の1号機を出荷
1977年、日本初のスーパーコンピュータ FACOM230-75 APU(注11)を開発(注8)汎用機「FACOM Mシリーズ」(出典: コンピュータ博物館 https://museum.ipsj.or.jp/)
*富士通の汎用機シリーズについて
国際化を狙うため,従来のFACOM 230-75やFACOM 230-8シリーズとは異なるIBM S/370(注12)が基本アーキテクチャとして採用された。1974年11月にFACOM Mシリーズの最初の機種FACOM M-190を発表。初期のFACOM Mシリーズは,FACOM M-190と後に追加された大型機FACOM M-180IIおよび FACOM M-160の合計3機種から構成され,FACOM 230-8シリーズの上位に位置する大型機シリーズであった。
(注9)超大型機「470V/6」
出典: 富士通日本ポータル https://global.fujitsu/ja-jp/
富士通と米アムダール社が共同開発し、1975年に完成したIBM互換超大型機。1号機は富士通が製造しアムダール製として同年、NASA(米国航空宇宙局)ゴダート宇宙研究センターに納入。このマシンは同センターが所有していたIBM360/165の2倍の計算速度を持ち、また当時IBM社でも設置から稼働まで通常2~3週間を要していたところ、5日で問題なく稼動。NASAでの1号機の噂は業界に伝わり、また高性能でありながらIBM機より低い価格を設定したこと等により、アムダール社の大型コンピュータはその後米国市場に受け入れられていった。
(注10)IBM互換機
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
IBMが開発した汎用コンピュータSystem/360やSystem/370との互換性をもつ汎用コンピュータ。日立製作所のHITAC Mシリーズや、富士通のFACOM Mシリーズなどを指す。
(注11)スーパーコンピュータ FACOM230-75 APU
出典: 富士通日本ポータル https://global.fujitsu/ja-jp/
1977年(昭和52年)に完成した日本で初めてのスーパーコンピュータ。FACOM230-75にアレイデータを処理するAPU(Array Processing Unit)を付加、FACOM230-75とFACOM230-75 APUとは非対称マルチプロセッサを構成した。プログラミングのために、標準FORTRAN仕様をベースにベクトル処理を効率的に記述できるAP-FORTRAN仕様を提供。1号機は1977年8月に航空宇宙技術研究所で運用が開始された。米CRAY社のベクトル計算機 CRAY-1(注13)からわずか1年後のことだった。
(注12)IBM S/370
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1970年6月30日にIBMが発表したメインフレーム・コンピュータのシリーズ名およびコンピュータ・アーキテクチャ名でSystem/360ファミリの後継である。System/370は、System/360
との互換性を保ち、性能向上に加えて商用初の仮想記憶をサポートした。System/360に続くSystem/370の成功により、コンピュータ市場でのIBMの影響力は圧倒的となった。
(注13)Cray-1
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
シーモア・クレイ率いるクレイ・リサーチ社が設計したベクトル型スーパーコンピュータである。この種類のコンピュータの基本構成を確立し、当時世界最高速であった。最初のCray-1システムはロスアラモス国立研究所に 1976年に納入された。Cray-1のアーキテクトはシーモア・クレイ、主任技術者はクレイ・リサーチの共同創設者であるレスター・デーヴィスだった。 |
|
川内 栄一
(かわうち えいいち) |
関川村湯沢出身。
1958年5月1日生まれ。
関小学校、関谷中学校、村上高等学校(29回生)を経て、1978年4月富士通電算機専門学院入校。
1979年4月富士通代理店、国際電子入社。特別区向け、財務会計システム、クレジットカード会社向けシステム、メガバンク向けシステムなどを開発。
2023年10月に退職。埼玉県戸田市在住。 |
 |
| 筆者近影 |
 |
| 1977年筆者 |
 |
(注1)売上伝票用紙
インプリンタ装置(注2) |
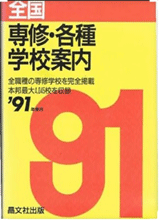 |
| (注5)全国 専修・各種学校案内 |
 |
| (注7)超大型機「470V/6」 |
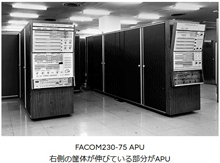 |
| (注8)スーパーコンピュータ FACOM230-75 APU |
 |
(注11)米CRAY社のベクトル計算機
CRAY-1 |
|
|