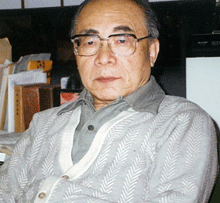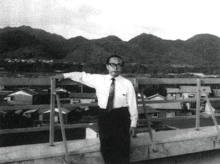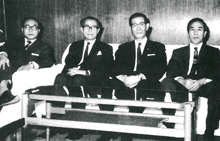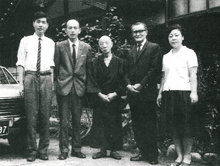| |
||||||||||||||||||||
| リレー随筆 「鮭っ子物語」 No.262 |
令和7年8月発行 | |||||||||||||||||||
| 優秀な生徒、先生たちで活気に満ちていた村上女子高校時代(その3) |
||||||||||||||||||||
| 女子高は注目されて・・・ 創立記念として水上勉氏や杉村春子さんを迎えて行った講演の後も、生徒には出来るだけ内容のある講師のお話を聞いてもらいたいと考え、私としても努力した。 翌年は歴史学者で現在も多くの著書が読まれている林屋辰三郎氏(京都大学名誉教授)、その次がドイツ文学者、随筆家としてやはり多くの著書が出ている高橋義孝先生に村上までお出でいただき、中身の濃いお話を生徒、先生方とともにお聞きすることができた。 また東京音楽大の卒業生が母体の東京二期会によるコーラス公演も行うことができた。林屋氏とはその後も手紙でのやり取りが続き、大工町の私の寺へもお出でいただいたりし、私も京都の上賀茂のお宅へ伺ったり個人的なお付き合いをさせていただいた。 開校して間もない村上女子高校には、優秀な女子生徒を入学(出願)していただけるよう、郡内中学校長会の熊田先生が各中学校にお願いしておられたこともあって、本当に優秀で明るい生徒が集まった。先生方も含めて活気に満ちていた。 セピア色の制服とベレー帽も、当時としては斬新なもので、修学旅行で関西方面に行くとよく「私立の学校ですか」と訊ねられ、「いえ、公立です」と答えると「公立でこんなハイカラな制服は珍しい」などと言われたものだった。 ただ、目立つ制服のうえ、地域住民も注目していたためか、村上高校や、村上桜ケ丘高校のような男女共学校であれば男子生徒と歩いたり、相合傘をしても別に何も言われないのに、村上女子高校の生徒が他校の男子と同じことをすると、「女子高の生徒は」と、何かと言われたのはかわいそうでもあった。 あのベレー帽にしても、髪型がくずれると思っていた生徒もいただろう。ヘアスタイルに気を遣う年頃でもあり、また他校の男子でも帽子をかぶらない生徒が増えていたこともあって、禁止はしなかったが、あまりやかましくは言わなかった。卒業生を送り出したのは2期生から。時代もあっただろうが、評判もよく、就職も良かった。 定年となって私が村上女子高を去るのは昭和49年3月だが、実は同46年には光済寺の住職になっていた。父・成中が病気だったため、父が先のことを考えて名目だけは早めに私に住職を譲っていたのだった。 父の教え「遊化」後に理解 村上女子高の校長時代のある朝、※西堀栄三郎先生がひょいと大工町の自宅(寺)に来られたことがある。 驚いて「先生、何ですか」と訊ねると、「コシヒカリのうまい朝食をいただこうと思って・・・」と言う。面白い人で、私が「うちはお寺でそんな贅沢なご飯は食べていませんが」と答えると、それで十分というのでその日は座敷で私の父と3人で朝食を摂った。聞けば西堀さんは講演で酒田市に向かう途中、下車したという。佐渡時代以前から手紙のやり取りがあって、村上にも何回かお出でいただいたが、楽しい人であった。 私の父・成中はその頃、自宅で療養中だった。新潟大学病院で胃がんの摘出手術を受け、その後、村上総合病院に移って治療を受け、退院していたのだった。そんなこともあって昭和46年に父は住職を私に譲っていた。真宗は世襲制となっている。 一高から東大、そして大学教授を経て住職となった父は穏やかな人柄で、檀家の方々にも慕われていた。私自身も毎日父の生活ぶりを目にして、ひそかに「立派な生き方だ」と尊敬の念を持っていたものだ。東大時代、社会学の権威だった建部教授の書生をしながら父は学校に通っていたという。その教授は大変気が短い方だったそうで、周囲の人たちは父をよく、最後まで仕えられたと感嘆していたと聞く。私にとっても言い尽くせない、大きな存在だった。 その父が亡くなったのは昭和48年の8月25日。享年88歳だった。 翌49年の3月に私も60歳の定年退職を迎えた。旧制村松中学校の教員になってから、約30年、村上女子高校の校長として教職にピリオドを打った。 教員生活の前半は、戦時中に教員に採用されたこともあって、規則を守るということには厳しかったと思う。性格もあっての事だろうが、生徒には厳しく接し、村上高校時代は「おっかない先生だ」ともよく言われたものだ。当時は親も世間もそうした教員の姿勢を普通のことと容認していたものだった。振り返ると、あっと言う間の教員生活だった。 ところで拙寺の玄関には、小さな玄関に不似合いなケヤキの大衝立がある。そして表面には父の筆による「遊化(ゆうげ)」という文字が彫られてある。「押し付けではなく、自由な生活の中から自然に人を教化させる」という意味のようだ。 学校で言えば、「教壇に立って上から教えるのではなく、日常生活の何げない言行の中で、あるいは遊びを楽しむ中で教化する」ということだろう。この父の「教え」を私が真に理解したのは、教職を去ってからのことだった。(了) ***** 今回のリレーエッセイは、私の父の安冨良英(1913-2010)が著書『櫻陰比輯(おういんひしゅう)』(2007年いわふね新聞社編集)から「いわふね新聞社」の許可を得てその著書の一部(pp.76-80)を転載したエッセイです。(安富成良記) |
|
|||||||||||||||||||
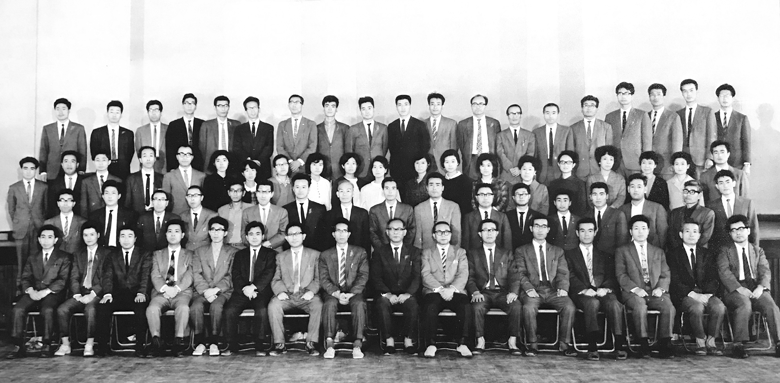 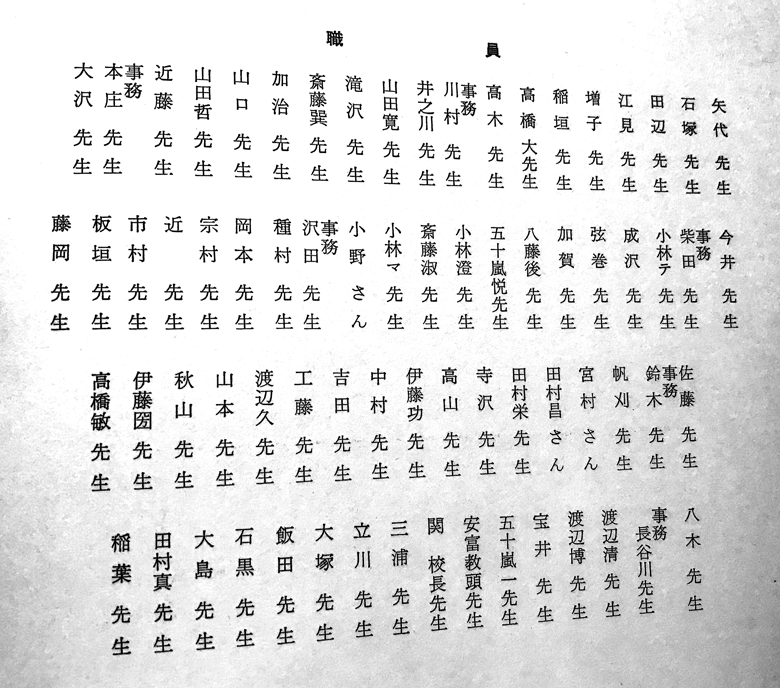 昭和41年当時の村高教職員 |
||||||||||||||||||||
| 東京村上市郷友会ホームページ リンク | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 表 紙 | WEB情報 | サイトマップ | バックナンバー | 検索・リンク 発行:デジタルショップ村上 新潟県村上市・岩船郡7市町村 月刊デジタル情報誌 2001年1月1日創刊 (c)2001~murakami21.jp All rights reserved Produce by Takao Yasuzawa |
||||||||||||||||||||